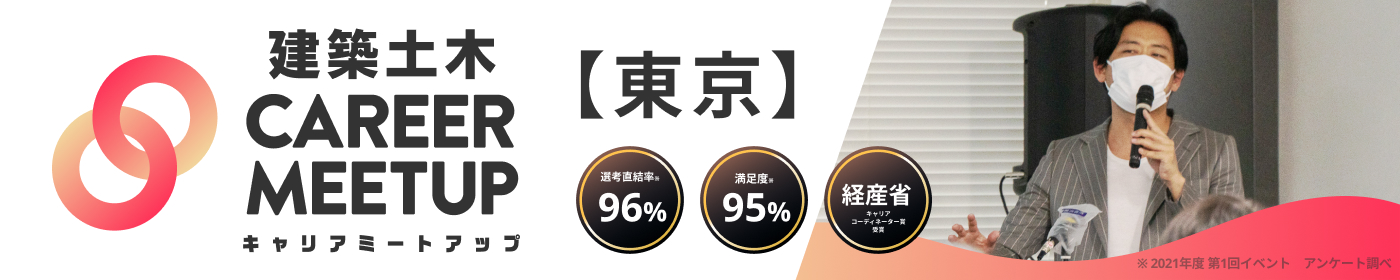より快適な空間を提案する「リフォーム・リノベーション」業界とは?

既存の建物に改修を行い、より快適に過ごしやすくするリフォーム・リノベーションという言葉は、学生の方々にも聞き馴染みがあるのではないでしょうか。特に、建築土木学生のみなさんの中にはそうしたリフォーム・リノベーション業界に興味を持たれてる方も多いと思います。
そこで今回は、リフォーム・リノベーション業界の詳しい仕事内容から、主な企業、業界自体のやりがい、現状や今後の動向まで、基本的な情報をご紹介します。イメージは何となく持っているけれど、詳しくは知らないという方は、業界研究の参考にしてみてくださいね。
この記事の目次
リフォーム・リノベーション業界の仕事について

そもそもリフォームとリノベーションの違いとは
リフォーム
一口にリフォーム・リノベーション業界と言っても、リフォームとリノベーションは少し違った点があります。
まずリフォームとは、古くなり、老朽化が進んだ建物を改修し、新しい状態に直すことを意味します。新しい状態に直すと言っても、新築以上の状態にはならず、あくまでも新築の状態に近付ける、といったイメージです。
建物自体のリフォームはもちろん、設備や庭などの改修を行う場合もあります。
また、リフォームはキッチン・風呂場・壁紙の修繕など、部分的な改修が多いところが特徴。リノベーションより工事の規模が小さいことも、違った点のひとつです。
リノベーション
先ほどご紹介したリフォームに対し、新築の状態に更に手を加え、機能や性能を上げて建物自体の価値を高めることをリノベーションと言います。つまり、既存の建物を新築以上の状態に引き上げるといったイメージです。
こちらも、建物自体のリノベーション以外にも設備等の面で改修を行う場合があります。
また、リノベーションは間取りの変更や解体作業といった全体的な改修が多い分野です。そのため、リフォームよりも工事の規模が大きいと言えます。
主な仕事内容とは

リフォームとリノベーションには規模等の違いがありますが、仕事内容に大きな違いはありません。
まず依頼を受けた建物について、営業職がクライアントの要望に合わせてデザインや設備の企画を行います。クライアントの要望に沿うことができるか、知識を活かすことができるかなどのスキルが必要とされます。
次に、決まった企画に沿って、設計・施工職の方の手によって工事が行われます。企業によって、自社の設計・施工職で工事を行う企業や他の企業に委託する企業があります。
主に営業職がクライアントとコンタクトを取り、リフォーム・リノベーションの具体的な提案や企画を行い、その企画にそって自社自身または他社に委託して設計・施工を行います。
リフォーム・リノベーション業界の主な企業

では、具体的にリフォーム・リノベーション業界にはどのような種類の企業があるのでしょうか。
リフォーム・リノベーション業界には主に3つの業態があります。
1つ目は、クライアントが所有している物件をリフォーム・リノベーションするものです。これを担う企業として専門業者やハウスメーカー関連会社が挙げられます。
2つ目は、物件を仕入れリフォーム、リノベーションを行い販売するものです。こちらは主に不動産会社が担う場合が多いです。
3つ目は、クライアントとともに中古物件を購入し相談をしながらリフォーム、リノベーションを設計施工するものです。こちらは、企業数は多くないですが、専門とする企業が行う場合が多いです。
上記に加え、住宅に関係する商品を扱う家電量販店などが、リフォーム・リノベーション業界に参入してきています。
近年の社会問題となっている空き家問題や、高齢化社会に向けて需要が高まってきている業界のため、さまざまな企業が参入していると言えます。
リフォーム・リノベーション業界のやりがいと向いている人は?

リフォーム・リノベーション業界の魅力とやりがい
リフォーム・リノベーション業界に共通するやりがいや魅力として、光を浴びることがなかった建物を、企画や施工を通して修繕し、再び蘇らせることができた際の達成感が挙げられます。また、それによってクライアントに満足してもらえることも、達成感を通じたやりがいに繋がると言えます。
また、知識も必要な職種になるため、自分自身が培ってきた知識を活かし、実際にリフォームやリノベーションが行われていく形を見ることは、やりがいや魅力に繋がるのではないでしょうか。
スキルは必要?リフォーム・リノベーション業界に向いている人とは
必要なスキル
リフォーム・リノベーション業界は、実際に知識を使って企画に携わったり施工に携わることも多い業界のため、リフォーム業界だと空間のデザインに関する知識が必要とされる「インテリアコーディネーター」、リノベーション業界だと、不動産を取り扱う際の知識が必要とされる「宅地建物取引士」などもスキルとして有利であると言えます。
いくつかの資格をご紹介しましたが、営業職などの職種であれば資格は必須ではありません。しかし、持っておくことで業界での仕事やスキルアップに役立つ場合があります。
向いている人
職種によって異なりますが、主に営業職では、クライアントの要望を上手く汲み取ることができる傾聴力のある人が求められます。また、リノベーション業界などでは「当たり前」に囚われることなくユニークな提案のできる人も向いています。
それと同時に、建物という規模の大きい商品を取り扱う上で責任感をしっかりと持つことができる人も向いていると言えます。
また、設計と施工を両方やってみたいという人にもおすすめの業界です。
リフォーム・リノベーション業界の現状と今後の動向

リフォーム・リノベーション業界の現状
責任感が大きい分やりがいを感じることができるリフォーム・リノベーション業界ですが、気になるのは業界の現状です。
先ほどもご紹介したように、近年の空き家問題や高齢化などの社会問題に貢献することができるリフォーム・リノベーション業界のニーズは高いと言えます。
国土交通省は、2010年に閣議決定した新成長戦略において、リフォーム・リノベーション業界について「2020年までに中古住宅流通市場やリフォーム市場の規模を倍増」を掲げており、国の後押しもある業界と言えます。
特に参入している企業も多い住宅の分野では、規模は横這いとなっており、手堅さのある業界であると言えます。
今後の動向をチェック
さまざまな企業が独自の指針を持って参入しているリフォーム・リノベーション業界は、この先もニーズが伸びていくと予想されます。
2016年には、国の住政策の方針である「住生活基本計画」において、2025年までに「リフォーム市場規模を7兆円から12兆円に向上」や「既存住宅流通の市場規模を8兆円に倍増」、「省エネ基準をクリアする既存ストックを2割以上にする」など、量と質共に向上させていくことを方針づけています。
また、リフォーム業界はもちろん、リノベーション業界もテクノロジーの進化によって、今後若者の注目を集めていくのではないかと考えられます。現代の社会問題や時代のニーズに沿うことができるため、今後も手堅い業界となっていくでしょう。
まとめ
今回は、リフォーム・リノベーション業界についてご紹介しました。クライアントの要望に沿いながら、既存の建物を再び改修によって蘇らせることのできるこちらの業界は、ストック社会である日本の現状を鑑みると、現状も今後においてもニーズのある業界であると言えます。
自分自身の興味や進みたい進路と照らし合わせながら、業界研究の一環として参考にしてみてくださいね。
スカウトで就活を有利に進めよう
コンキャリでは、建築土木就活における記事を多数掲載しており、またカンファレンスからES・面接対策まで大小さまざまな建築土木に特化したイベントに参加することができます。
また、コンキャリに登録すると平均5社以上のスカウトを受けることができ、就活を安心して進めることができます。
ただ5社のスカウトを受けるわけではなく、各建築土木学生の方の状況や志望領域に合わせた5社のスカウトを受け取ることができるため、就活をかなり有利に進めることができます。

みなさまの就活を応援しています!