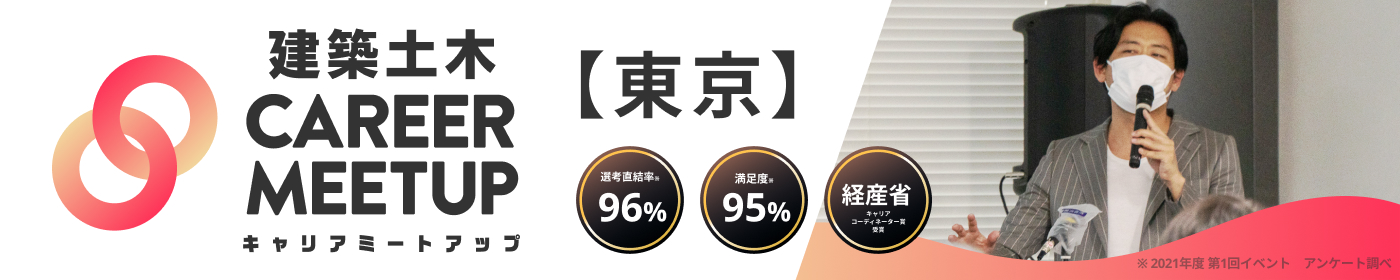建設コンサルタント業界は若い力を求めている!現状や課題から建設コンサルタントの将来性を考えよう

建設コンサルタントは、建設工事を統括する重要な役割を担うため、志望している建築、土木専攻の学生の方も多いのではないしょうか。建設コンサルタント業界を深く見てみると、ゼネコン業界とはまた違った現状や課題、そして将来性が見えてきます。
今回は建設コンサルタント業界の現状や課題、直近での新型コロナウイルスの影響なども踏まえたうえで、業界の今後の将来性、動向予測を紹介していきます。
建設コンサルタント業界を目指す学生は最後に現状や将来性から、今後どのような視点で就活を進めたらよいかを紹介しているので、ぜひ建設業界全体の理解を深め、今後の就活に役立ててみてください。
この記事の目次
建設コンサルタント業界の現状・課題
建設コンサルタント業界とは
建設コンサルタント業界の課題や将来性を説明する前に、建設コンサルタント業界の仕事や関連する資格などを知りたい方は、以下の記事で建設コンサルタント業界にについてご紹介していますので、ご覧ください。
建設業界における上流工程の担い手である「建設コンサルタント」ってどんな職業?
業界の市場規模
短期的な見方では、建設コンサルタントの仕事は増えると考えられています。
その理由として、2025年ごろまではオリンピックや万博などの大規模イベントがあるため、それに伴いインフラ整備に多額の投資が行われると予測されているからです。
しかし長期的な視点では約10年前のピークを機に減少傾向にあります。
その理由としては以下に挙げる建設コンサルタント業界の特徴と関係があります。
建設コンサルタント業界の特徴と市場縮小の背景
日本の建設コンサルタントの特徴としては、今までは行政が行う業務の補助がメインだったため、クライアントも行政が主体となり、行政のニーズに答えることに注力してきた背景があります。
しかし、近年は政府の厳しい財政事情により建設投資、公共投資の費用は減少傾向にあり、今後も縮小、維持傾向は変わらないとの見方が強く、中長期的に公共事業の市場の拡大は望めません。
労働者の高齢化問題
現在の建設コンサルタント業界の平均年齢は40歳を超えており、40代、50代の社員が多く、20代の若手社員が少ないという問題もあります。
業界の高齢化の理由としては、不況の時期に新卒や若手社員の採用を減らした影響もありますが、1番の原因は長時間労働などの過酷な労働環境により、社員の定着率が低いことが挙げられます。
20代、30代は結婚などのライフイベントも多く、近年の職場に対して、働きやすさを求める声が多くなっている傾向などからも、若手社員が将来のビジョンを描きづらい業界となっています。
海外事業
建設コンサルタントの海外進出の始まりは、昭和30年頃と歴史があります。
近年では海外進出の動きは活発になってきており、発展途上国のインフラ整備に着手しています。
しかし発展途上国の経済発展のために日本政府機関による出資である、政府開発援助(ODA)の規模は、財政面の緊迫化に伴い、縮小・維持傾向にあるため、こちらも中長期的な拡大は期待できません。
そして競争相手として中国をはじめとする新興諸国が加わったことなど、今後は価格競争力の強化や、民間の資金を用いた官民連携事業(PPP)に代表される非ODA事業の展開を考えていく必要があります。

建設コンサルタント業界のコロナの影響は?
新型コロナウイルスはコロナショックという言葉も存在するように、日本の経済にも大きな影響を与えています。
withコロナ、afterコロナの取り組みを各業界、企業が行なっている中、建設コンサルタント業界は新型コロナウイルスによってどのような影響を受けたのでしょうか。
建設工事の工程の遅れ
建設業界全体のコロナの影響として、建設工事の工程の遅れがありますが、建設コンサルタント業界もその影響を受けています。
またオリンピック事業に携わっていた企業などは、オリンピックの延期の影響も受けています。
しかし建設工事の工程の遅れにによって仕事自体は増えているため、ゼネコン業界などで懸念されている受注競争が激しくなるような動きは今のところないようです。
建設コンサルタントは企業によって、得意分野、専門分野が異なり、コロナによる影響も企業によって違います。
自分が興味がある企業はコロナによってどのような影響を受けているのか、そして今後の経営方針などを調べることによって、企業の特徴や将来性について知るきっかけになります。
海外事業の仕事の激減
コロナの影響は日本だけでなく、海外も同様に建設工事の遅れや中止といった影響を受けています。
多くの建設コンサルタント企業が海外事業に力を入れている中で、コロナによって海外事業の仕事激減してしまい、海外から国内に事業領域をシフトする動きを見せている企業もあります。
海外で働くことに興味がある場合は、コロナによって海外事業の方針や展開に動きや変化があったのかよく調べておきましょう。

建設コンサルタント業界の今後の展望
ではここまでの業界の現状や課題、新型コロナウイルスの影響などを踏まえたうえで、建設コンサルタント業界︎全体としての今後の展望を紹介していきます。
異分野への進出
建設コンサルタント業界では、現在建設業界以外の分野への進出を積極的に行なっています。
農業や観光、情報通信、発電など業界はさまざまで、今後建設業界が縮小することを見込んで、各企業が新領域を開拓する動きは今後も続きそうです。
建設コンサルタント業界にとって地方自治体との繋がりを強めることは、公共の調査・設計、維持管理などの本業の業務に繋がります。
建設分野だけでなく、多くの業界に進出することによって、地方自治体との関係を強め、建設コンサルタントの本業の受注につなげ、さらに新たな事業を軌道に乗せることで、新領域の開拓も成功させるという狙いがあります。
新技術への投資
建設コンサルタント業界は新技術の研究、開発も積極的に行なっています。
AI、3Dデータの活用など企業ごとに独自の技術を開発しており、本業や異分野で得た利益を研究、開発に回し、新技術を使って新たな仕事を取るという流れが業界全体のトレンドになっています。
働きやすい労働環境への取り組み
残業が多く、仕事が大変であるというイメージは建設コンサルタントに限らず、建設業界共通の課題ではありますが、労働環境の改善への取り組みも行われているようです。
ノー残業デイの設定や、決められて時間でのPCの強制シャットダウンなど企業によって独自の取り組みが行われています。
また建設コンサルタンツ協会内で、ビジネスモデルや働き方といった業界展望を考えるための若手有志組織が作られるなど、業界全体での動きもあるようです。
労働環境に関しては、各企業が現在整備を進めている段階で、今後も若手社員などの声を参考に、改善が進められていくでしょう。
海外事業への取り組み
海外事業に関しては、コロナによって国内事業へシフトする企業もありますが、今後も国内需要の縮小が予想される中、新たな収益基盤として期待されていることは変わりません。
今後は海外企業との競争がある中で、日本の特性を生かした質のよいサービスの提供するための施策が問われています。
企業によって、現地法人や新事務所の開設、現地企業のM&Aなど海外進出の取り組みも異なるため、海外事業拡大への取り組みの理由や背景を調べ、企業の特徴を知るきっかけにも繋げてみましょう。

学生が就活で持つべき視点とは
ここまで建設コンサルタントの現状や、これからについて紹介してきましたが、建設コンサルタントに興味がある学生はどのような視点を持って就活に取り組めば良いのでしょうか。
業界や企業への理解を深める
建設コンサルタント業界を目指すうえで、まず重要になってくるのが業界、企業への理解です。
業界や仕事に対する理解が低いまま入社してしまうと、やりがいが感じられなかったり、早期退社の原因にもなります。
建設コンサルタント業界全体としても、人の入れ替わりが多く、人材の定着率向上は1つの課題になっています。
残業時間が長い企業が多いなど、業界の良い面だけでなく、大変な部分や課題などをしっかりと理解したうえで就活をするようにしましょう。
自分の専門分野だけでなく、広く様々なことを学ぶ
学生の時代に専門分野をしっかりと学び、論文の作成などに力を入れることも大切になります。
しかし、就職後は必ずしも自分の専門分野を活かせる仕事ができるとは限らず、そこで入社前とのギャップを感じてしまう場合もあるようです。
建設コンサルタントの事業の分野は今後も広がっていくことが予想されることからも、自分の専門分野以外にも広く様々なことを学ぶ姿勢を意識しましょう。
若手ならではの視点を意識する
建設コンサルタント業界の平均年齢が上がっている中で、学生に対して魅力ある業界になるためには、今後どのような改善が必要かということを学生の段階から考えることは重要です。
企業側としても若手社員が働きやすい業界にするためにはどうすればよいかを考えるにあたって、学生の意見は参考になります。
今回紹介した現状や課題、将来性などを参考にして、自分はどのように建設コンサルタント業界を変えていきたいかという大きな視点を持って就活に臨んでみましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
業界の現状や課題、今後の展望を理解することは就活において重要ですが、理解を深めたうえで自分の考えや意見を持つことが就活では大切になります。
建設コンサルタント業界は課題も多く、今後に向けての変化が進められている業界ではありますが、若者の労働力や意見は多くの場面で必要とされています。
学生の皆さんはぜひ、就活でも受け身にならず、建設コンサルタント業界を変えていくためにはどうすべきか、自分はどう変えていきたいのかという意見を持って就活に臨むようにしましょう!
スカウトで就活を有利に進めよう
コンキャリでは、建築土木就活における記事を多数掲載しており、またカンファレンスからES・面接対策まで大小さまざまな建築土木に特化したイベントに参加することができます。
また、コンキャリに登録すると平均5社以上のスカウトを受けることができ、就活を安心して進めることができます。
ただ5社のスカウトを受けるわけではなく、各建築土木学生の方の状況や志望領域に合わせた5社のスカウトを受け取ることができるため、就活をかなり有利に進めることができます。

みなさまの就活を応援しています!