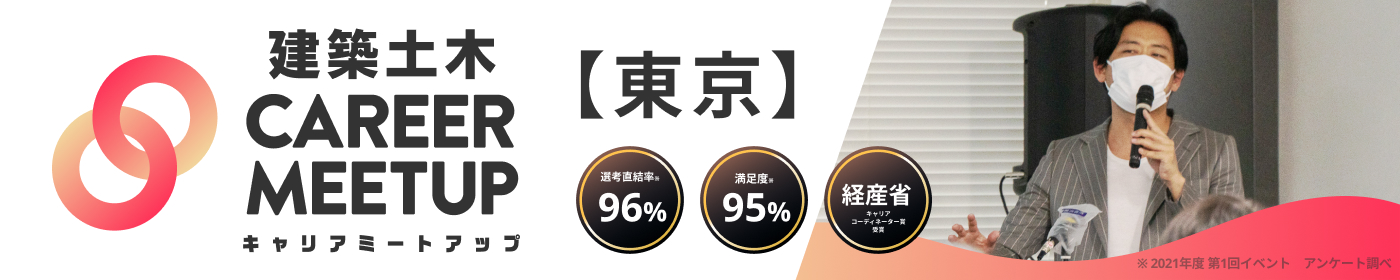建物を建てるためには土の調査から!地質調査技士ってどんな資格?

建物を建築する際に一番最初に必要になるのが、その土地の地質を調べるという作業になります。
今回は、地質調査を行うときに取得しておきたい資格である、地質調査技士について仕事内容や資格の概要について詳しく説明していきたいと思います。
この記事の目次
地質調査技士について
地質調査技士とは
地質調査業務のうち、現場でボーリング操作や工程管理や安全管理、地質の計測・試験を行い報告書を作成するための知識と技能を認定する公的資格です。
なぜ地質調査が必要?
安全な建築物を立てるためにまず最初に重要なのは、安全な土台を作ることです。建築物は年々巨大化、高層化しています。
地質調査を行わずに地耐力が十分でない土地に建物を立てると、後に建物が傾いてしまったり、一部の保険に加入することができなくなってしまうなどのリスクがあります。
そのため地質調査を行い地盤の強さを調べ、地耐力が基準に達していなければ、地盤改良工事を実施するなど、建物を安心して作るための地盤を作っていきます。
また、日本は自然災害が多い国なので防災計画を作成するうえで、地中のすべりやすさ、崩れやすさなど災害に備えるための調査も行うことがあります。

地質調査技士の仕事内容
では地質調査技士を取得すると、具体的にどのような仕事を行うのでしょうか。
地質調査でよく使用されるボーリングマシンなどの機械の操作だけではなく、地質調査を行う前の周辺の調査や、資料集め、現場スタッフに調査の進め方について指示を出すなど、現場の安全管理や工程管理、調査データの分析、判定を行います。
そして、その結果をまとめた報告書の作成まで現場での作業からオフィスワークまで多岐に渡ります。
勤める企業によって仕事内容は異なりますが、実際の工事に加え、調査の工程のマネジメントをする能力も要求される仕事になります。
地質調査技士の資格について
地質調査技士の資格はボーリング試験やトンネル工事、土壌改良などの実務に携わる技術者が受験し、取得していることが多いようです。
地質調査の仕事をするのに必ずしも地質調査技士の資格は必要ではありません。しかし、現場での活躍の幅を広げるため、また企業によっては資格の取得によって月手当が支給される場合もあるので、土木系の仕事を希望している人であれば取得しておきたい資格の1つです。
資格の種類とそれぞれの特徴
地質調査技師は現場調査部門、現場技術・管理部門、土壌・地下水汚染部門の3部門に分かれ、それぞれ受験資格を得るまでの実務経験の年数などが異なります。ここでは部門ごとの受験資格、試験形式を紹介していきます。
現場調査部門
ボーリング・マシンのオペレーションなど、ボーリングに関する機器などの操作を行う方向けの試験を行います。
受験資格を得るにはボーリング実務経験を通算5年以上、または協会が指定する指定学科卒業のうえ、2年以上の実務経験を積む必要があります。現場調査部門の試験は筆記試験と口頭試験です。
筆記試験は選択式問題と記述式問題の2種類があります。また、3部門の中で唯一口頭試験があるのが特徴です。
現場技術・管理部門
地質調査に関する現場の管理業務や物理探査、土質試験、計測業務などを実施する方向けの試験です。
受験資格は大学および工業高等専門学校(5年課程)で、地質・土木・建築・地球物理学などの地質調査に関する課程を卒業した方は関連する実務経験3年以上、それ以外の方は5年または8年以上の関連実務経験が必要となります。
試験の形式は筆記試験のみで、選択問題と記述問題になります。
土壌・地下水汚染部門
土壌・地下水汚染調査を含む地質調査に関する、現場管理や調査・計測業務を実施する方向けの試験です。
受験資格は大学および工業高等専門学校(5年課程)で環境・地質・土木などの地質調査および環境に関する課程を卒業した方は関連実務経験3年以上、それ以外の方は5年または8年以上の関連実務経験が必要となります。
こちらも試験の形式は筆記試験のみで、選択問題と記述問題になります。

地質調査技士の合格率
近年のデータを参考にすると地質調査技士の合格率は3部門とも30%から40%が合格ラインとなっています。他の資格と比べても難易度は平均的と考えられていますが、建築行政や土木・建築設計の知識、入札契約制度などの問題も出題されるため、幅広い分野での知識が要求される試験になります。
地質調査技士の資格の対策としては過去問や参考書、問題集などが入手できるので、実際の現場での経験を踏まえながら対策をするのが一般的です。
また、地質調査技士の資格の有効期間は5年間と決められています。それ以降は5年毎に「講習会の受講形式」、あるいは、「継続教育CPD記録の報告形式」のいずれかを任意選択し、登録更新手続きが必要になります。
地質調査技士の就職先、将来性
ここまで地質調査技士のしかくについて詳しくご説明しましたが、地質調査技士の所持者はどのような職業に就く人が多いのでしょうか。
例としては、地質調査会社、ボーリング業、総合建設会社、建設コンサルタント、設計会社などさまざまです。デベロッパー、ハウスメーカー、官公庁などから地質調査、設計施工管理を請け負うため、活躍する場も幅広い資格と言えます。
将来性
地質調査技士の資格は、公共工事の質や安全性を担保する資格であるため、「公共工事の品質確保の促進に関する法律(以下、品確法)」という法律と密接に関わっています。
そして平成26年度の品確法改正を踏まえて、公共工事の品質確保を目的とした技術者資格登録制度が開始され、平成27年度に3部門すべてが登録技術者資格として登録されました。そのため企業にとっても資格の保有者の重要性は高まり、活躍の幅も広がっています。
また、土木工事に関わる方も地質調査技士の資格と共に測量士、建築士、技術士、土木施工管理技士など関連性の高い国家資格を取得することで関わることのできる仕事の幅を広げ、キャリアアップにつなげることも可能になります。
まとめ
いかがでしたか。
一度建物が建つと、その土地の地面は人の目に触れることはあまりなく、その状態を把握することも難しくなります。。しかし、私たちが安心して利用できる建物を建てるためには土台となる地質の調査は欠かせません。
地質調査技士の資格は特定の学科を卒業していないと、受験資格を得るまでの実務経験の年数が長くなってしまいます。
現在建築、土木学科で学んでいる学生は学校で得た知識を元に、少ない実務経験年数で受験資格を得ることができるので、資格取得のハードルは他の方と比べても低いと言えます。
今回の記事で地質調査技士の資格に興味を持った方は就職後に資格の取得に挑戦してみてください!
スカウトで就活を有利に進めよう
コンキャリでは、建築土木就活における記事を多数掲載しており、またカンファレンスからES・面接対策まで大小さまざまな建築土木に特化したイベントに参加することができます。
また、コンキャリに登録すると平均5社以上のスカウトを受けることができ、就活を安心して進めることができます。
ただ5社のスカウトを受けるわけではなく、各建築土木学生の方の状況や志望領域に合わせた5社のスカウトを受け取ることができるため、就活をかなり有利に進めることができます。

みなさまの就活を応援しています!